「今夜の自己採点、どう進めればいい?」──終わった直後こそ手順が命。私は“再現→採点→次の一手”をテンプレ化して、翌日のモヤモヤを最小化しました。この記事は、そのまま使える採点シートと、点数帯ごとの翌日の動き方をまとめた保存版です😊
自己採点の基本フロー(15分で完了)
① マーク再現 → ② 正解照合 → ③ 判定メモ
- 問題冊子に残したメモと記憶で再現解答を作成(迷った選択肢も記録)。
- 公式解答または信頼できる速報で正誤を照合(確証度も残す)。
- 翌日の行動を点数帯テンプレに当てはめ、必要な手続きを先に押さえる。
そのまま使える|自己採点テンプレ(コピペOK)
再現解答シート
| No. | 自分の解答 | 正解 | 結果 | 確証度 | 迷いメモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○/× | 高/中/低 | |||
| 2 | ○/× | 高/中/低 | |||
| 3 | ○/× | 高/中/低 | |||
| … |
集計・判定メモ
- 業法:__/___点 民法:__/___点 法令:__/___点 税・その他:__/___点
- 合計:__点(±不確定__問)
- 再確認が必要な設問:No.__, __, __
- 翌日のアクション:(下の点数別テンプレからコピペ)
点数別テンプレ|翌日の動き方
① 40点台前半〜(合格可能性が高い帯)
- 翌日やること:受験番号控え・自己採点表の保存。登録実務講習や今後の手続きの情報収集。
- やらないこと:不確定1〜2問に固執しない。消耗を避けて次の準備へ。
- 次の一手:合格後の手順とキャリア計画を整理。
👉 学習の土台を再点検:フォーサイトで宅建業法を得点源に|暗記しやすい構成で合格
② 36〜39点(ボーダー帯)
- 翌日やること:再現解答の精度を上げる(迷いメモの論点を条文・定義で再確認)。
- 情報の扱い:ボーダー速報は参考に止め、公式発表まで行動は保留。
- 次の一手:合格時・不合格時の両方のプランをメモ化(手続き/学習再開の開始日)。
👉 よく出る論点の再確認に:本試験で“ほぼ出る”テーマ10選【2025年版】
③ 32〜35点(次年度に向けて早期リスタート)
- 翌日やること:弱点3領域の特定(業法・民法・法令のいずれか)。
- リカバリー:翌週から週3回×30分の軽め復習で“勘”を維持。
- 次の一手:通信講座や教材の見直し。アウトプット中心設計に変更。
👉 学習設計の最適解を確認:宅建は独学と通信講座どちらがいい?通信講座で合格した私の結論
④ 31点以下(仕切り直し計画を当日で完成)
- 翌日やること:「開始日・教材・過去問サイクル」の3点を決める。
- 短期戦略:“基礎の積み直し→業法で先に点を作る”へ舵切り。
- 次の一手:週次の可視化(学習ログ/模試予定/月次テーマ)。
👉 スキマ時間の積み上げ法:宅建受験者におすすめのアプリ5選|スキマ時間で効率アップ
ミスの洗い出しテンプレ(コピペして使う)
エラーの分類
- 知識不足:条文・定義の未記憶(例:報告義務の頻度、契約不適合の通知期限)
- 読み違い:否定・例外の見落とし、数値の取り違い
- 戦略ミス:時間超過、二択処理の基準なし、見直し不足
- オペミス:マークずれ、消し残り、頁またぎの取り逃し
翌週までのToDo(合否確定前の安全運転)
- 再現解答の最終保存(クラウドと紙)
- 弱点3論点のミニ復習(各15分×3)
- 合格時手続きの流れを読む(登録・実務講習の概要)
- 不合格時の学習キックオフ日をカレンダーに登録
FAQ
- Q. 自己採点で迷いが多い。合否の見方は?
A. 合計点に不確定数を明記し、上下幅で把握。幅が大きい場合はボーダー情報に一喜一憂しないこと。 - Q. ボーダー速報はどこまで信用する?
A. 参考材料に止める。最終判断や手続きは公式発表待ちが安全です。 - Q. 次年度の再挑戦はいつ開始が良い?
A. 記憶が残っているうちに1〜2週間以内に軽い復習を再開。その後ペースを整えます。 - Q. 点数が低くて心が折れそう…
A. 原因を「知識・読み・戦略・オペ」に分解すると具体策が見えます。次回の伸び代が特定できます。
関連おすすめ記事
- 9月は過去問強化月間!宅建本試験で“ほぼ出る”テーマ10選【2025年版】
- フォーサイトで宅建業法を得点源に|暗記しやすい構成で合格
- 試験まで60日!宅建短期集中スケジュール【9月連休活用版】
- 宅建は独学と通信講座どちらがいい?通信講座で合格した私の結論
- 宅建受験者におすすめのアプリ5選|スキマ時間で効率アップ
まとめ|採点は“幅”で見て、動きは“テンプレ”で決める
今夜は「再現→照合→幅の確認→翌日の一手」をテンプレ通りに。迷いはメモ化して次の判断材料へ。合否が出るまでの時間を、次に効く行動に変えましょう。
\応援クリックしてもらえると嬉しいです/


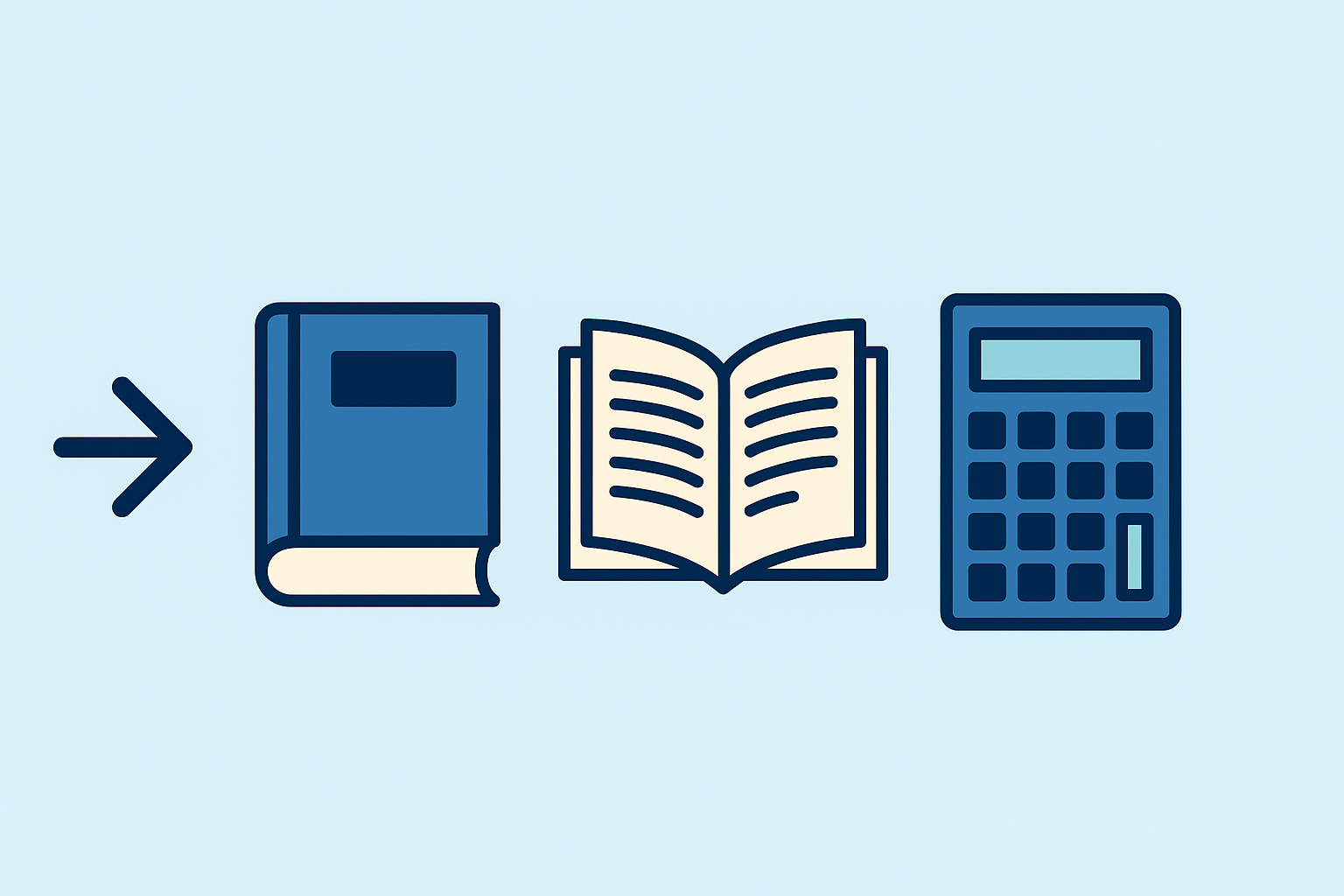
コメント