宅建試験では毎年、受験生を惑わせる「ひっかけ問題」が多数出題されます💦
私も最初は「内容は覚えてるのに正解できない…」と悔しい思いをしたことが何度も。でも、ひっかけパターンを知っておくだけで正答率がグンと上がるんです!
この記事では、9月の総仕上げにぴったりな「宅建ひっかけ問題パターン集」と、本番で失点を防ぐコツをご紹介します✨
なぜ宅建試験に“ひっかけ”が多いの?
宅建試験は知識量だけでなく、正確さや読解力も問われる試験です。
そのため、あえて「似た選択肢」や「まぎらわしい文言」を使って、うっかりミスを誘う問題が多くなっているんです。
👉 模試で点が取れない人の対策法では、「読み間違いによる失点」の具体例や、ひっかけ問題への耐性を高める復習法を解説しています。
宅建の“ひっかけ”問題パターン集
1. 数字が微妙に違う
例:35日→30日、8年→10年など。
→ 日数・年数系は「○日以内」「○年以上」の表現に注意!
2. 「できる」「しなければならない」の違い
例:「~することができる(任意)」と「~しなければならない(義務)」は意味が真逆。
→ 動詞の助動詞レベルで引っかけられます。
3. 「売主」「買主」の立場をすり替える
業法や民法でありがち!
→ 文中に「売主」「宅建業者」「一般人」などの記述がある場合、誰の立場かを意識して読みましょう。
👉 頻出テーマを優先して対策したい方は、宅建過去問出題頻度ランキングをチェックして、ひっかけの出やすい分野に集中しましょう。
4. 「例外」なのに“通常のルール”で答えさせる
例:「一定の場合を除き…」と書かれているのに、例外のケースが出てくる問題。
→ 例外条件があるときは要チェック!
5. 語尾の否定「〜ない」で惑わす
問題文が「正しいものを選べ」なのに、選択肢が「〜ではない」と否定形だと混乱しやすい😖
→ 問題の指示(正しいのか誤りか)と選択肢の語尾を冷静に確認!
6. 「聞かれていること」が途中で変わる
長文の民法問題などで、「前段と後段で別の視点を問われる」タイプ。
→ 問題文は最後まで読んでから選択肢に行くこと!
👉 焦って読み飛ばしてしまう方は、宅建試験の問題を解く順番と時間配分のコツも合わせて読んでみてください。
本番で“ひっかけ”に強くなるコツ
・音読で読み間違いを防ぐ
試験本番では声に出せませんが、普段の過去問演習で音読すると「誤読しやすい箇所」に気づけます。
・選択肢を先に読まない
先に選択肢を読むとバイアスがかかりやすいです。まずは問題文をしっかり読んでから取り組みましょう。
・「絶対に◯◯」など極端な表現は要注意
「必ず」「一切認められない」などの選択肢は、ひっかけの可能性大。例外があるか確認を。
・集中力が落ちた時は一度リセットを
読み違いの大半は「疲れ」や「焦り」が原因です。
👉 集中できない日の対処法を取り入れて、本番でも頭をクリアに保ちましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q. ひっかけ問題は毎年出るんですか?
A. はい。宅建は毎年必ず数問、ひっかけ要素を含んだ問題が出題されます。 - Q. 苦手な人はどう対策すれば?
A. 過去問で“なぜ間違えたか”を記録することが重要です。同じパターンで間違えないように意識しましょう。
関連おすすめ記事
- 宅建過去問出題頻度ランキング
- 模試で点が取れない人の対策法
- 【2025年版】宅建の合格点は何点?
- 宅建試験の問題を解く順番と時間配分のコツ
- 落ち込んだとき、どう立て直した?|宅建合格まで続けられたメンタルリセット術
まとめ|ひっかけパターンを知れば怖くない!
・宅建の“ひっかけ”はパターン化されている
・語尾・数字・立場・例外に注意する
・過去問と模試を活用して「読解力」と「判断力」を鍛えよう
\応援クリックしてもらえると嬉しいです/

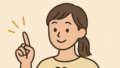

コメント