宅建試験まで、いよいよ残り30日。
「この時期でも全部覚えきらなきゃダメ…?」と焦っている方、ちょっと待ってください。
合格者の多くは、本番で“捨て問”を見極め、確実に取るべき問題で点数を積み上げていました。
この記事では、直前期に知っておくべき「捨て問の判断基準」と「本番の時間配分テクニック」を解説します。
宅建の“捨て問”とは?
捨て問とは、次のような問題です:
- 出題頻度が極端に低いマニアック分野
- 過去問と傾向が大きく違う応用問題
- 時間をかけても正解率が低い計算問題
合格点(例年35点前後)を取るには、全問正解する必要はありません。
「取れる問題で確実に得点する」ことこそが、合格の鉄則です。
▼出題頻度を見ながら優先順位をつけたい方はこちら
ラスト30日で“切るべきテーマ”例
以下のようなテーマは、暗記負担が大きく得点効率も低いため、優先度は低めです:
- 統計問題(数値丸暗記)
- 住宅金融支援機構の細かい規定
- 瑕疵担保責任と買主保護法制度の例外
もちろん、時間に余裕があれば対策して損はありませんが、今から詰め込むなら、頻出分野を優先しましょう。
時間配分のコツ|科目別の目安と順番
本番で焦らないためには、以下の配分をベースに「自分なりのルーティン」を持っておくことが重要です。
- 宅建業法(20問):35分…最初に解いて得点を稼ぐ
- 法令上の制限(8問):15分…暗記系なのでスピード重視
- 税・その他(3問):10分…計算ミスに注意
- 権利関係(14問):30分…後半に回して集中力勝負
▼時間配分の詳細や解く順番はこちらで解説しています
マークミス防止&焦り対策のワザ
- 先にマーク欄だけ全て塗っておく(番号ずれ対策)
- 残り時間15分で「確実に取れる問題」を再確認
- 迷ったら「直感で1つ選ぶ→印をつけて飛ばす」
9月は「満点を狙う」より「合格点を超える」戦略を
ここまで来たら、100点満点の勉強ではなく、「35点を確実に超えるための戦略」をとりましょう。
過去問・苦手テーマ・時間配分。3つに絞って毎日こなせば、十分合格は狙えます。
▼30点台→40点台に伸ばしたい方はこちらも参考に👇
まとめ|やるべきことを減らす=合格への近道
・捨て問は「正解率が低い+出題頻度が低いもの」
・時間配分を決めて、取れる問題から確実に解く
・9月は「やらないこと」を決めると合格が近づく
\応援クリックしてもらえると嬉しいです/

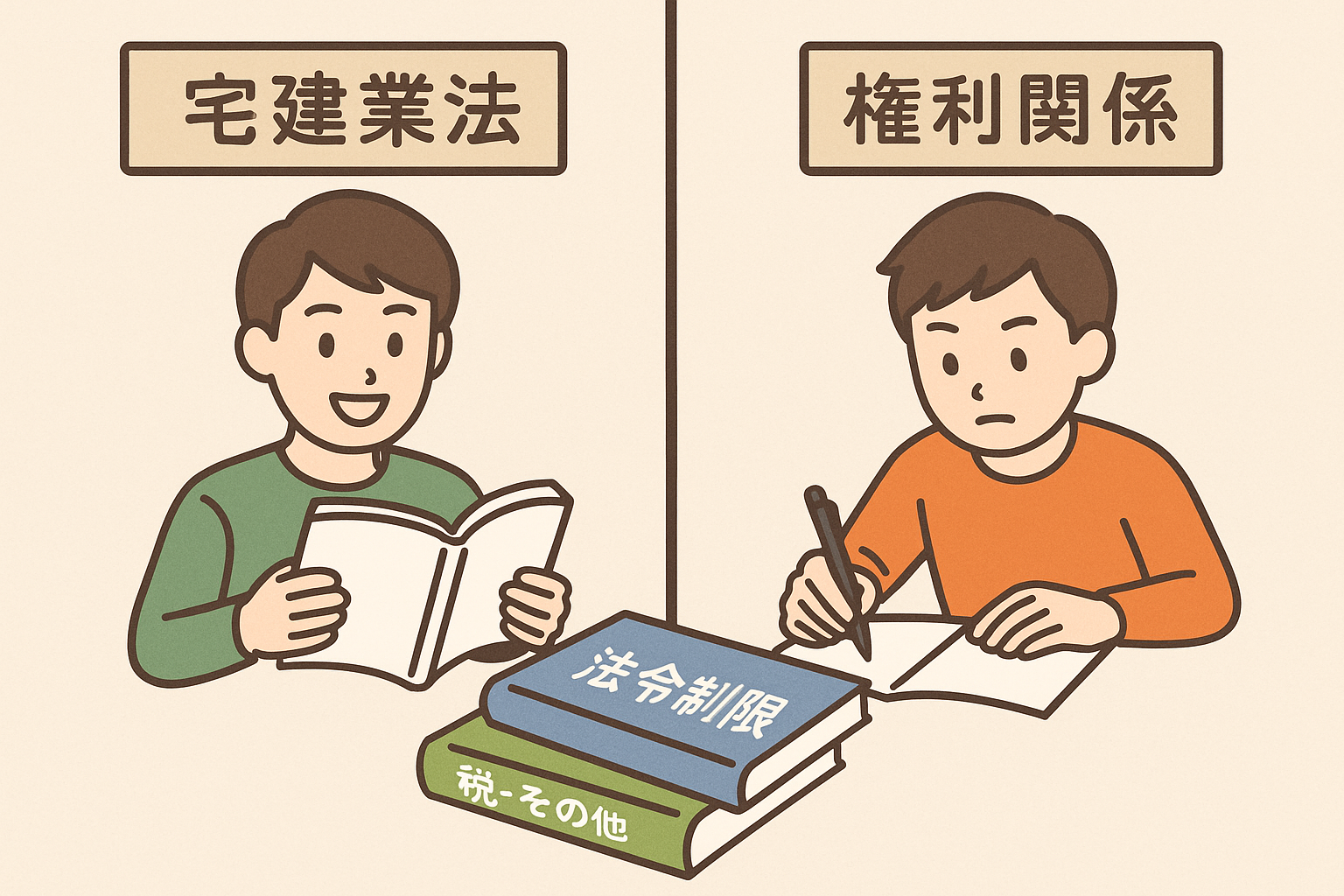

コメント